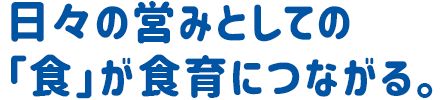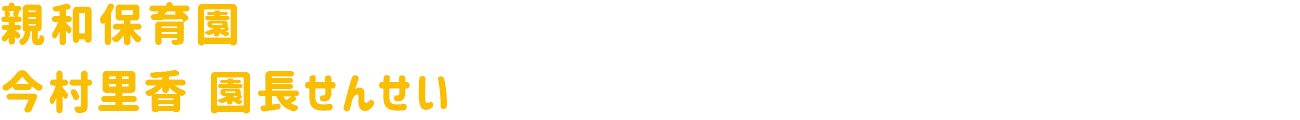


「食」は保育の土台、
保育の原点だと思います。
「食育」と特別に意識して始めたわけではありません。ただ、保育において食事は“土台”にあるべきもの。私が若い頃に勤めていた保育園でも、「食は保育を支えるもの」という考えが根付いており、その姿勢を今も大切にしています。この園は開園して22年になりますが、開園当初、調理を担当してくださっていた方は、料理の彩りや盛り付けに心を込める方で、その丁寧な姿勢が職員にも広がっていきました。給食ではなく「食事」。保育者も調理者も、こどもたちの食べる様子に気を配り、日々の食卓の風景をつくりあげていく。そうした積み重ねが、今の「園の食」をかたちづくっています。園で野菜を育てるようになったのも、そんな日常の延長です。みんなで夏野菜を植え、育て、収穫し、調理して食べる。それはこどもたちにとって遊びであり、学びであり、暮らしそのもの。朝の登園時、調理スタッフが「とうもろこしの皮、むいてくれる?」と声をかけると、「やりたい!」と嬉しそうに集まってくるこどもたち。「自分たちで育てた野菜だから食べてみよう」「調理のお手伝いをしたから食べてみよう」と、苦手だった食材にも自然と手が伸びる姿があります。


食材を通じた地域とのつながりも
大切にしたい。
食材は、できるだけ地産のものを選ぶようにしています。具体的には、できるだけ地域の個人商店から仕入れるようにしています。お米屋さん、お肉屋さん、八百屋さん、魚屋さん、パン屋さん・・・。それぞれの専門店で仕入れることは、園を支えてくださっている地域の方々への感謝の気持ちもあります。さらにプロたちから食材にまつわる話も直接うかがえるので、私たちにとっても学びの機会にもなっています。黒鯛が海苔の養殖場を荒らして困っているという話を伺い、それなら園でも協力しようと黒鯛を食事のメニューに取り入れました。神戸のために何かできることがあれば、神戸にある園として協力したい。園から見えるまちの風景は、確実にこどもたちの食卓につながっています。

「おいしいね」の一言が
こどもたちを育てます。
食事の時間は、こどもたちにとって“みんなで楽しむひととき”です。「家では食べないものも、園では食べる」と保護者から驚かれることも少なくありません。大人が「おいしいね」と笑いながら同じメニューを食べる。その姿をこどもたちに見せることが大切です。お昼前、出汁の香りが園内にふわっと広がると、「今日のごはんはなに?」と調理室をのぞきに来ます。「今日はうどんだって!」と会話がはずむ。そんな幸せな空気がこの園には満ちています。「食育」という言葉が独り歩きすることもありますが、私たちにとって「食」は日々の暮らしそのもの。こどもたちと一緒に季節を感じ、その日の食材と向き合い、みんなで味わう。特別なプログラムではなく、日々のなかで繰り返される「食」の時間が、こどもたちの心と身体を育てていくと、私たちは信じています。